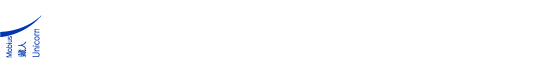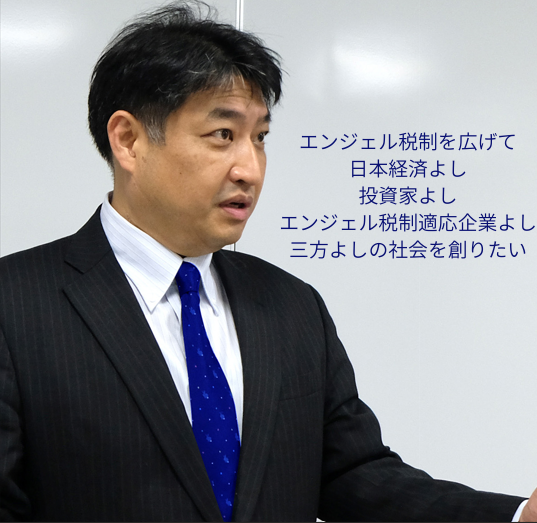第20号:多角化経営を餓死線上にしない事業経営会社トップの仕事とは!

前回のコラムでは、コングロマリッドビジネスの本質について、コングロマリッドビジネスオーナーが本来の仕事に集中することで、富だけでなく自由な時間が増えるビジネススタイルであるということを述べさせて頂きました。
今回のコラムでは、グループ経営最適化状態におけます事業会社トップの仕事について述べさせて頂きます。
ところで、グループ経営最適化状態におけます事業会社のトップの仕事とは、一体、何だと思われますか?
事業会社の売上・収益を極大化する事業経営者でしょうか?
アメーバ経営のように、独立採算性の視点から効率の良い経営を行う事業経営者でしょうか?
あるいは、コングロマリッドビジネスオーナーへの報連相を怠らず、人格に富んだ事業経営者でしょうか?
これらはいずれも、事業会社トップの仕事の一部ではあります。
しかし、あくまで枝葉の一部の一部にすぎません。
そもそもグループ経営最適化のもとにあるコングロマリッドビジネスとは、どういうビジネススタイルだったでしょうか?
グループ経営最適化のもとにあるコングロマリッドビジネスとは、会社が2社になれば売上が2倍、3社になれば3倍といった“足し算のモデル”ではありません。
お互いがキラー経営資源を磨き合い、共鳴し合うことで、「1+1=3」どころか「1+1+(キラー経営資源強化分)=10」にもなるような乗数効果を発揮させるビジネススタイルです。
事業会社のトップには、この“乗数効果”を最大限引き出す経営が求められるのです。
そこで、グループ経営最適化状態における事業会社トップの仕事は、三つに整理されます。
第一に、基幹事業とともにキラー経営資源を強化し合う経営を行うこと。
第二に、お客様の要求を満たし続けることで、事業会社のビジネスモデルを刷新し続け、次なる新規事業進出の資金を生み出せる経営を行うこと。
第三に、将来の事業会社トップを生み出す“孵化機能”をもたせる経営を行うことです。
まず一点目につきましては、
グループ経営最適化状態におけるコングロマリッドビジネスは、通常のビジネスとは新規事業の着眼点そのものが異なります。
通常のビジネスでは、「儲かりそう」「成長しそう」といった市場の外形要因から事業を選びます。
そして、アメーバ経営に代表されるように単体での利益責任で評価されます。
各々のビジネスが単体での利益追求を行っているため、赤字の新規事業は孤立状態に陥り、援軍が来ない中で餓死線上をさまよい、最後は撤退を余儀なくされます。
一方、グループ経営最適化状態においては、新規事業は、「この事業は、基幹事業とキラー経営資源を強化し合えるか?」という視点から生み出されます。
仮にうまくいっていない新規事業があったとしても、他の事業会社からキラー経営資源の強化という“援軍”が送られ、その援軍のお陰で、再起のチャンスが何度でも与えられるのです。
そして、新規事業が成長すれば、今度は自らが援軍を出す側に回り、基幹事業のキラー経営資源強化に、更なる貢献をするようになります。
グループ経営最適化状態にあるコングロマリッドビジネスとは、
こうして、コングロマリッドビジネス全体が“強く、しなやかな相互支援体制”のもと拡大し続けるのです。
重要なことは、グループ経営最適化状態における優れた事業経営とは、独立採算性の数値だけで評価されるものではないという点です。
あくまで基幹事業との間でキラー経営資源を強化し合い、グループ全体を大きくできるポテンシャルを持ち得ているかが重要なのです。
したがって、新規事業は“業界のマージナルサプライヤー(限界供給者)”で何ら問題はありません。
実際、17回目のコラムでも述べました通り、マージナルサプライヤーの集積こそが、他社に模倣されない“強いビジネスの集合体”を創るのです。
次に、二点目につきましては、
お客様の要求を満たし続けることで、事業会社自身のビジネスモデルを刷新し続け、次なる新規事業進出の資金を生み出す経営を行うことです。
企業はお客様の要求を満たすことで、売上と利益を得て社会に貢献する存在です。
だから、お客様との直接面談の中で、市場のニーズを学ばせて頂くという考え方に欠如した事業会社のトップは論外です。
そして、お客様のニーズを満たし続けた結果、事業会社は黒字経営であるべきです。
ただし、それだけでは不十分です。
単に会社を黒字にすれば良いのではなく、「コングロマリッドビジネス全体を前に進めるための“新たな原資”」を創出できるレベルの収益が求められます。
マネジメントの父ピーター・ドラッカーは、こう言いました。
“The purpose of a business is to create and keep a customer.”
「企業の目的は、顧客を創造し、維持することである。」
つまり、事業会社のトップは“顧客に向けた価値創出”に100%集中し、その結果、新規事業の原資を創りうる財務基盤を整える責任を担うのです。
三点目は、将来の事業会社トップを生み出す孵化機能を持たせる経営です。
コングロマリッドビジネス全体の成長は、将来の事業会社の社長・副社長を量産できるかどうかにかかっています。
だからこそ、各事業会社でも、将来の事業会社の社長・副社長を量産できる体制を築かなければなりません。
そのためには、事業会社ごとに「経営指針書」を整備し、社員一人一人の願望と、事業会社の重要経営指標をリンクさせる仕組みが必要です。
社員の将来設計が、会社の成果と直結する組織の中で、社員は会社に定着し、やがて、事業会社の社長・副社長は生まれるのです。
経営指針書の作成と運用には、「社員が、自らの未来を会社の成長と結びつけて語れる」ような仕掛けが必要です。
その責任を担うのが、まぎれもなく、事業会社のトップなのです。
最後に、最も重要なことを申し上げます。
コングロマリッドビジネスオーナーがオーケストラ全体の“指揮者”であるように、事業会社のトップもまた、“自社というオーケストラの指揮者”でなければなりません。
指揮者が楽器を吹いてはオーケストラは成立しません。
社長自らが課長・係長レベルの判断に忙殺され、社員の日常行動を逐一管理し、24時間365日働きづめで疲弊していては、的確な経営判断ができなくなります。
事業会社のトップこそ、自らの時間を確保し、創造的な思考を巡らせ、未来を構想する時間を持つのも事業会社トップの仕事なのです。
トップが疲弊していては、クリエイティブな戦略など生まれません。
そのような事業会社は、コングロマリッドビジネス全体に貢献する存在には、決してなれません。。
事業会社トップの真の仕事とは、
「事業会社単体の利益責任を追う事業経営者」ではなく、「コングロマリッドビジネス全体に乗数効果を生み出す真の経営者」なのです。
そして、一番大事なことはコングロマリッドビジネスオーナーが事業会社のトップを、会社のトップとして扱うことから全て始まるのです。