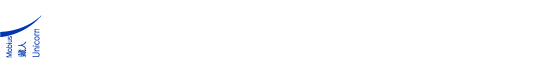【第15回:●●戦略に基づかない決算時期の決定はグループ全体に巨額の損失を生む!】
日本では、3月決算を採用する企業が多くあります。
しかし、その理由については、あまり知られていないように思います。
実は、日本企業の多くが3月決算を採用する理由は、国家予算が3月31日で締まるからなのです。
では、一体、どのような経緯で、日本政府の決算は3月になったのでしょうか?
日本政府が3月決算になった経緯は、国家や国民のためにプラスになる大義名分があった訳ではありません。
日本政府が3月決算となった理由は、明治政府の台所事情にあったのです。
明治元年は1868年10月23日に始まります。
明治政府の当初の方針は、欧米の基準に合わせようというものでした。
そこで、明治政府の決算時期は、明治2年から9月になりました。
その後、明治6年には12月、明治8年には6月、明治17年に3月と
明治政府は、3回も決算時期を変更しました。
明治政府は、財政破綻に陥りそうになる度、会計年度を短くすることで乗り切っていたのです。
なぜ、明治政府は、こんなに頻繁に、明治政府は決算時期を変更したのでしょうか?
一点は、戊辰戦争や士族の反乱に戦費が必要だったことです。
もう一点は、地租に依存した税の徴収方法が、明治政府を慢性的な財源不足に陥らせていたからと言えます。
結局、明治政府の財政は、明治20年所得税導入、明治32年法人税導入で安定し始めます。
その後も、大きな出費はありましたが、日清戦争は国債で乗り切りました。
日露戦争は、ヤコブシフを初めユダヤ財閥の国債購入と相続税、物品税(消費税)の導入で乗り切りました。
太平洋戦争も国債で賄いましたので、明治17年以降、日本政府は決算を変えることなく、今に至っています。
日本政府の決算月が3月になったのは、このような経緯なのです。
因みに、台湾、韓国も3月が予算の締めです。
余談ですが、イギリスも、イギリスの旧植民地の多くも、3月締めです。
日本で3月決算の企業が多い理由には、合理的な理由は無いわけですから、
決算期は、自らの会社運営が最適化するよう、各々の会社が決定すべきなのです。
小売業、商社であれば、メーカーの決算の一ヶ月前の2月決算を採用すれば、
有利な仕入れを行え、収益向上が図れます。
建設業等、公共からの発注が多い産業であれば、
3月はバタバタしていますので、公共がらみの発注で忙しい3月からプラス2ヶ月ずらします。
5月、11月を決算期にすれば、社内の事務処理間違いが減り、会社運営は最適な方向に向かいます。
宿泊業、旅行業であれば、年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇等を避けることで、
社内処理の間違いが減り、会社運営は最適な方向に向かいます。
グループ経営を行っている企業グループの場合、
グループ全体で大きな収益を出していて、節税を志向している企業グループであれば、
税務署に、利益通算制度の適応届を出して、利益通算制度を導入します。
その場合、グループ会社の決算は揃えなければなりません。
ところが、グループ経営を行っている企業グループの中に赤字会社が多く、直接金融や間接金融による資金調達が必要な状態であれば、利益通算制度は導入せず、決算時期をずらします。
特に、グループ間の売り買いが多い場合には、180度真逆(ある会社は2月ある会社は8月)にします。
新設法人の場合、設立時期と決算期を調整することで、消費税の納税義務免除期間を最大限活用することもできます。
このように、私がコンサルティングに入るときは、徹底的なヒアリングを行った後、各々の会社の決算時期最適化を行います。
コングロマリッドビジネスを志向されたい企業には、
グループ経営最適化に基づき、利益通算制度が採用出来る構成を作ります。
そして、利益通算制度を取らない場合の最適決算月、利益通算制度を取った場合の最適決算月を決定します。
このように、決算時期の決定は、会社の命運を担う重要な決定事項なのです。
全社戦略に基づかない決算時期の決定を行う会社からは、多くのお金が逃げていくことになるのです。