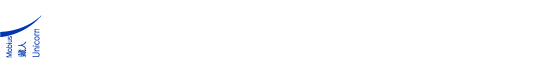【第17回:多角化で失敗したくなければ業界トップ3に入れない事業に手を出さないは嘘?】
楽天モバイルの苦戦を嘲笑する動画がSNSを中心に出回っています。
彼らの論調は、「三木谷氏は、孫正義氏の携帯電話事業進出時と異なり、インフラ投資を軽視したので、上手くいくはずが無い。」
「設備投資が多い産業では、業界ナンバー4以下は立ちゆかない。」というものです。
本当に、そうなのでしょうか?
私は、三木谷氏の楽天モバイルは、ある重要な論点に沿った多角化であり、最終的に、楽天全体が上手く回っていく起爆剤になるのではと考えています。
そこで、本日のコラムは、「多角化経営が業界トップ3に入れない新規事業に手を出すことは悪なのか?」というテーマで進めて参りたいと思います。
まず、限界生産者という言葉を聞いたことがありますでしょうか?
限界生産者とは、業界のトップ3に入っていない、“どんぐりの背比べ状態”に位置する生産者や供給者を指します。
業界トップ3にある企業は、規模の経済が働き、生産コストを抑えることが可能です。
一方、限界生産者は、生産コストが高いため、需要が増加している時には売上が伸びるものの、需要が減少すれば真っ先に売上を失い、撤退を余儀なくされます。
そのため、多くの経営書やMBAの講義では、限界生産者になってはならないと繰り返し教えられます。
例えば、あるスーパーマーケットに複数の卸業者が商品を納入していたとします。
コロナ禍で買い物客が減った場合、どうなるでしょうか?
そのスーパーマーケットでの売上シェアが高い上位3社の卸は、それほど売上を落としません。
ところが、4位以下の卸は棚を奪われ、大きく売上を落とします。
仮に、この4位以下という状態が、他の取引先でも続いていれば、その卸の経営は危機的状況に陥る可能性があります。
こうした構図から、「新規事業において限界生産者になりそうな事業には手を出してはいけない」という馬鹿げた主張が出てくるのです。
私は、この馬鹿げた主張に真っ向から反対します。
二回目、六回目のコラムでは、2つの成功したコングロマリッドビジネスにおける24の新規事業について取り上げてきました。
実は、そのうち23事業が、“限界生産者”としてスタートし、現在も、”限界生産者“として存在しています。
もし「業界トップ3に入れない事業は手を出すべきではない」という考えが絶対であるならば、
これら2つのコングロマリッドビジネスは、新規事業が足を引っ張り、早々に頓挫していたはずです。
ところが、実際はどうだったのでしょうか?
限界生産者として存在していた、これらの事業群こそが、基幹事業の発展を加速させる起爆剤となっていたのです。
なぜ、限界生産者として不利な位置にいた事業が、全体を押し上げる原動力となり得たのか?
その理由は、私のコンサルティングでも常に最重要視している五つの視点の一番重要な点を抑えていたからです。
これまでのコラムで述べさせて頂きました通り、5つの視点は以下の5点になります。
①新規事業が、基幹事業の“キラー経営資源”を強化する方向性に沿っていたこと。
②事業経営者の選定が正しく行われていたこと。
③後継者候補も含め、事業経営者を量産する人事システムが整っていたこと。
④拡大の資金が、キラー経営資源の磨き上げによって得られていたこと。
⑤社員の願望と会社の生産性向上が数字でリンクしていたこと。
この五つの条件の中でも、何より大事なのは①です。
“キラー経営資源の強化”という絶対軸さえ保たれていれば、例えその事業が限界生産者であっても、
それはグループ全体にとって、強靭な臓器の一つとして機能し得るのです。
コングロマリッドビジネス全体を人の身体に例えるならば、これらの23事業は、業界内では限界生産者かもしれませんが、
それぞれが肝臓、腎臓、心臓、肺…といった多機能な臓器として役割を果たしていた。
結果として、“全身が健康で強靭な企業体”が構築されていたわけです。
逆に、失敗を恐れて「最初から業界トップ3に入れそうな事業を探して」事業展開を行った場合、どうなるでしょうか?
一つの臓器を患った場合、その悪影響が、他の臓器にも転移し、一気に体調を崩してしまうのです。
まさに、見かけは立派な筋肉質でも、内臓機能の弱い身体と同じです。
こうした“個別最適の集合体を創る思考“こそが、グループ経営を不安定にする要因となりうるのです。
楽天モバイルの話に戻りましょう。
確かに、楽天モバイルは今、単体で見れば赤字が続いています。
ですが、私はこの新規事業は、楽天の“キラー経営資源”を明確に強化する事業だと見ています。
楽天の方向性は、楽天経済圏の構築という言葉で片付けられがちですが、
楽天市場、楽天カード、楽天銀行、楽天証券…といった、巨大なID連携プラットフォーム全てが、楽天を儲けさせて頂いている御客様に向いてはいないでしょうか?
楽天モバイルを加えることで、IDによる情報統合、ロイヤリティの強化、データ資産の拡充が一気に加速し、楽天を儲けさせて頂いている御客様の利便性向上につながりはしないでしょうか?
楽天モバイルは、“楽天グループ全体”のキラー経営資源を磨く動きなのです。
さらに重要なことは、キラー経営資源強化の方向で事業展開する利点は、
楽天モバイルが「赤字だから」と揶揄されることで、競合が誰も後追いしない点にあります。
“キラー経営資源強化”という軸を保った限界生産者の組み合わせでビジネスを創ることは、真似されない独自ポジションの確立にもつながるのです。
つまり、限界生産者を選ぶこと自体が問題なのではありません。
その事業が、グループ全体のキラー経営資源を強化するものであるか否か。
そこに判断軸を持てるかどうかが、成功か失敗かを分ける絶対条件なのです。
私は、限界生産者を“否定”するのではなく、“戦略的に活かす”ことで、真の強さが生まれると信じています。
限界生産者の組み合わせが、強いコングロマリッドビジネスを創るのです。